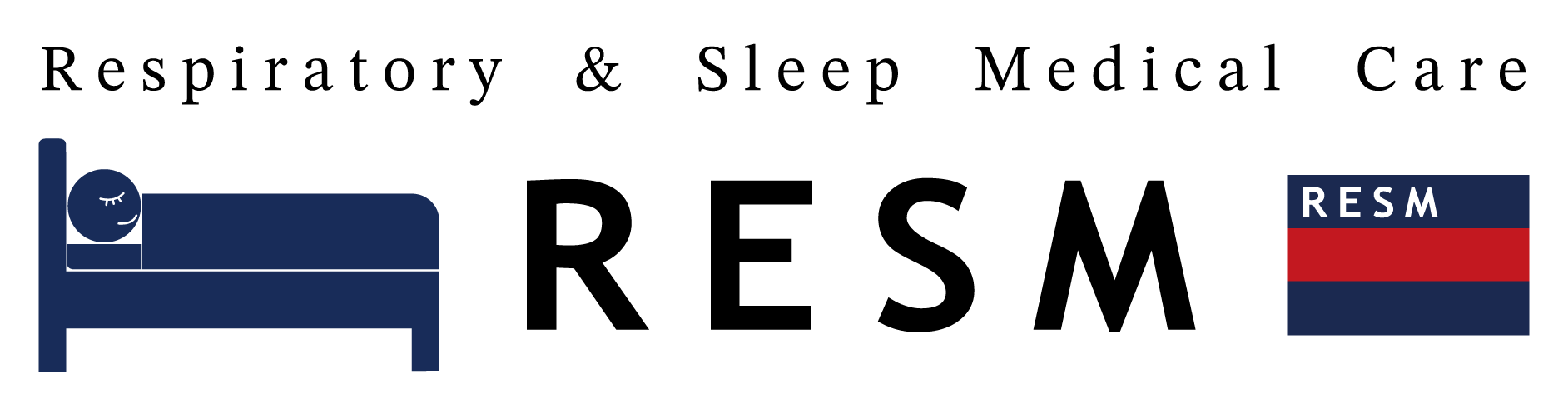睡眠薬のウソ・ホント|誤解されがちな睡眠薬の真実を専門医が解説

はじめに|「睡眠薬=怖い薬」ではありません
「睡眠薬って依存性があるんでしょ?」
「飲み続けたら頭に悪いんじゃないの?」
「寝られないけど眠剤は怖いのでなるべく我慢している」
——こうした声は、日常診療のなかで本当によく耳にします。
確かに、睡眠薬には注意すべき点がある一方で、
「正しく使えば、安全で効果的な治療薬」であることもまた事実です。
しかし、ネットやテレビ、あるいは身近な人の体験談だけで
睡眠薬に対する「偏ったイメージ」だけが広がっているのも現実です。
このコラムでは、睡眠専門医の視点から、睡眠薬にまつわるよくある誤解を「ウソ or ホント」の形式でひも解きます。
それぞれの噂に対し、科学的な根拠・リスク・最新の分類や使い方の工夫まで丁寧に解説していきます。
「なんとなく不安で睡眠薬を避けていた」
「家族が飲んでいて心配」
そんな方にこそ、読んでいただきたい内容です。
ウソ or ホント?:睡眠薬を飲んでいると“ボケやすくなる”
よく聞く不安の声
「うちの母、最近なんだか物忘れが増えて…眠剤のせい??」
「睡眠薬って、認知症のリスクが高くなるんでしょ?」
こうした不安の声は、外来でもたびたび耳にします。
確かに、「睡眠薬=認知症の原因になる」というイメージは、広く浸透しています。
でも、本当にそれは「睡眠薬のせい」なのでしょうか?
ホント:一部の薬には注意が必要
結論から言うと、この噂は半分ホントです。
ホントの側面
過去からよく使われている「ベンゾジアゼピン系」や「非ベンゾジアゼピン系」の睡眠薬には、
次のようなリスクが報告されています。
- 高齢者ではせん妄・転倒・記憶障害のリスクが上がる
- 長期連用で注意力や作業記憶の低下が見られる場合がある
- 一部の疫学研究では、アルツハイマー型認知症との関連性が示唆されている
特に、高齢者が長期間ベンゾジアゼピン系薬を服用した場合、
脳の可塑性が弱まり、認知機能に影響を及ぼす可能性は否定できません。
すべての睡眠薬に当てはまるわけではない
一方で、現在はベンゾジアゼピン以外の新しいタイプの薬が登場しています。
よく使われる睡眠薬と認知機能への影響
| 薬のタイプ | 例 | 認知機能への影響 |
| メラトニン受容体作動薬 | ラメルテオン(ロゼレム) | 少ない |
| オレキシン受容体拮抗薬 | スボレキサント(ベルソムラ)、レンボレキサント(デエビゴ) | 少ない(研究段階だが安全性は高め) |
| 非ベンゾジアゼピン系 | ゾルピデム(マイスリー)、エスゾピクロン(ルネスタ)など | 注意は必要だが、用量・期間で調整可能 |
| ベンゾジアゼピン系 | トリアゾラム(ハルシオン)、ブロチゾラム(レンドルミン)など | 高齢者への投与には注意が必要 |
つまり、「睡眠薬=認知症になる」というのは短絡的すぎる言い方で、
薬の種類・年齢・用量・使用期間によってリスクはまったく異なるのです。
レンボレキサント(デエビゴ)というオレキシン受容体拮抗薬の薬効と合併症を調べた研究では、レンボレキサントを不眠症の方3名に投与すれば1名は不眠症の改善につながること(NNT=3)、その一方で治療によって副作用を自覚する人は10余名にひとり(例、日中の眠気を自覚する人が投与者15~28名にひとり)ということが報告されています。レンボレキサントの有効性と安全性を同時に示されている研究といえます。1)
また、レンボレキサントを1年以上服用した場合の副作用についての研究でも、認知機能への影響は特に指摘されていませんでした。2)
オレキシン受容体阻害薬やメラトニン受容体刺激薬は認知症に関して関与が疑われる報告は現段階では認めていません。
以上を踏まえ、どの薬を服用するのか医療機関での相談を行っていくことが重要です。
メラトニン受容体刺激薬やオレキシン受容体拮抗薬について詳しく知りたい方は下記のコラムもご覧ください。

怖くなるのは当然。正しく理解を
認知症のリスクを防ぎたいなら、次のような対応が大切です。
睡眠薬による認知機能への影響を最小限にするコツ
- 医師と相談しながら、定期的に見直す
- 高齢者にはベンゾジアゼピン系をなるべく使わない/短期にとどめる
- 新しいタイプの薬への切り替えを検討する
- 薬だけでなく、生活習慣の見直しも同時に行う
薬が悪いのではなく、薬の使い方が非常に重要です。
注意点を理解しながら、安全に・上手に使うことを心がけましょう。
ウソ or ホント?:一度飲み始めると、一生やめられない?
睡眠薬を始めることへのためらい
「眠剤って、始めたら最後、もう手放せなくなるんでしょう?」
「クセになりそうで怖いから、できるだけ飲みたくない」
そんな理由で、明らかに睡眠の質が低下しているのに、治療をためらっている方が少なくありません。
“薬をやめられなくなる恐怖”は、睡眠薬に関する最も根強い誤解のひとつかもしれません。
ホント:特定の睡眠薬には依存性あり
こちらも一部ホントです。
確かに、一部の睡眠薬には「身体的依存」や「精神的依存」が生じる可能性があります。
依存のリスクが比較的高い薬
- ベンゾジアゼピン系(例:トリアゾラム、ブロチゾラムなど)
- 非ベンゾジアゼピン系の一部(例:ゾルピデム、エスゾピクロンなど)
これらの薬は、長期間の使用で耐性(同じ容量では効果が薄くなる)ができたり、
急にやめると離脱症状(不眠・不安・けいれんなど)が出たりすることもあります。
そのため、「一度飲んだら一生やめられない」と感じてしまっても無理はないでしょう。
非ベンゾジアゼピン系は、催眠効果があり、即効性も高いため我々も処方するお薬です。ベンゾジアゼピン系に比べて、依存性を抑えながら催眠作用を残しているお薬ですが、依存性がゼロというわけではありません。長期間の使用では耐性・離脱症状の報告は認められていますから、処方開始時にはリスクについても触れながら開始していくことが望ましいでしょう。
適切な使い方なら、やめることは可能
あらゆる睡眠薬について、一生飲み続けなければならないわけではありません。
以下のようなポイントを守れば、安全に減薬・中止することが可能です。
睡眠薬を無理なくやめるために大切なこと
- 医師の管理のもとで、少しずつ減薬していく
- 睡眠環境や生活習慣の見直しも同時に行う
- 認知行動療法(CBT-I)などの非薬物療法と組み合わせる
- 状態が安定していれば、薬を“補助的な道具”と考える
実際、診療の中でも「不眠がつらかった時期に一時的に薬を使い、今は飲んでいない」という方もいらっしゃいます。
また、依存性が少ない新しいタイプの睡眠薬(メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬)も登場しており、元来の睡眠薬のイメージとは異なる内容の処方がしやすくなっています。
一生やめられない薬ではなく、「一時的な手助け」として
「薬を飲む=依存してしまう」という考え方には、少し偏りがあります。
睡眠薬は、「眠れないというつらさ」から心と体を守るための、
一時的な“橋渡し”として用いるべき道具です。
- つらい時期に一時的に支えてもらう
- 状態が安定したら生活習慣や治療にシフトする
- 少しずつ“自分の眠り”を取り戻していく
そうした使い方をすれば、睡眠薬は「一生付き合わねばならないもの」ではありません。
また、ここまでの説明から、すでに内服中のお薬に不安を感じた患者様もいらっしゃると思います。しかし、一過性のストレスなど特定の状況に関してはベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬のほうが使用しやすいことも事実です。
すでに処方されている薬にはきっと理由が存在します。主治医の先生と現在の処方薬について相談を行うのも、あなたの不安が和らぐ一つのきっかけになるかもしれません。
ウソ or ホント?:“眠くなる薬”なら何でも同じ?
眠れたら、それでいい?
「市販の風邪薬を飲むと眠くなるから、それで代用してる」
「抗不安薬を少しだけ飲めば眠れるし、問題ないですよね?」
こうしたご相談をいただくことがあります。
確かに、“眠気をもたらす薬”は睡眠薬以外にも多く存在します。
しかし、それらは本当に「安全な代用品」なのでしょうか?
ウソ;「眠くなる薬=睡眠薬」ではない
眠気を引き起こす作用のある薬は、たとえば以下のようなものです。
眠気をもたらす薬の一例
| 薬の分類 | 主な例 | 本来の目的 |
| 抗ヒスタミン薬 | ジフェンヒドラミン(市販の風邪薬・睡眠改善薬) | アレルギーや風邪症状の緩和 |
| 抗うつ薬 | ミルタザピン(リフレックス)、トラゾドン(レスリン)など | うつ病や不安症の治療 |
| 抗不安薬 | エチゾラム(デパス)、クロチアゼパム(リーゼ)など | 不安や緊張の緩和 |
| 抗精神病薬 | クエチアピン(セロクエル)など | 統合失調症などの治療 |
これらの薬が眠気を誘うのは副作用であって、本来の効能ではないことが多いのです。
そのため、睡眠薬代わりに使うと、以下のようなリスクが生じます。
- 用量が適切でない(効きすぎたり、朝まで残る)
- 本来の疾患の病状に必要な容量以上に薬を使ってしまう
- 薬剤相互作用や副作用のリスクが読みにくい
- 医師の管理外での管理になりやすい(市販薬など)
「質のよい眠り」には、適切な薬を
睡眠薬は、「入眠」「中途覚醒」「早朝覚醒」など、
不眠のタイプに合わせて処方が選ばれるよう設計されています。
また、薬剤の効果時間や体内での代謝の仕方も考慮し処方を行っています。
たとえば…
- 「入眠困難」には作用が短いタイプ
- 「中途覚醒」や「早朝覚醒」には作用が長めのタイプ
- 高齢者には、筋弛緩作用やふらつきが少ないもの
こうした細やかな選択ができるのが、医師が処方する“本来の睡眠薬”の強みです。
使用の目的を意識して、薬と付き合う
花粉症や不安をおさめる薬の一部には眠気を催すものがあることは確かです。
眠気以外を目的に服用している薬物であれば休薬が困難なこともあるでしょう。
そのうえで、「なかなか寝付けない」「途中で目覚めてしまう」など違った原因が合う睡眠薬はきっと存在します。
満点の睡目指すことはむつかしいかもしれませんが、今よりも良い睡眠のために処方内容の見直しを行っていきましょう。
ウソ or ホント?:睡眠薬は脳にダメージを与える?
巷で広がる「脳への影響」を心配する説
「睡眠薬を長く飲むと、脳細胞が壊れるって本当ですか?」
「将来、認知症になりやすくなるんですよね?」
こういったご不安の声を、患者さんからしばしば伺います。
インターネットやSNS上には、「睡眠薬=脳に悪い」というイメージが根強く存在しているように感じます。
ですが、その多くは誤解や過剰な一般化によるものです。
一部ホント:一部の薬ではリスクがあることも事実
たとえば、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や抗ヒスタミン薬の一部(長期使用)に関しては、
一部の研究で高齢者の認知機能低下や転倒リスクなどの関連が示唆されています。
ただし、ここで重要なのは次の3点です
- 用量・使用期間・年齢などでリスクが変わる
- すべての睡眠薬に当てはまるわけではない
- 不眠自体が、認知機能に悪影響を与えるというデータもある
つまり、「睡眠薬=脳に悪い」という話は、一部の条件に当てはまるケースを過度に一般化したものなのです。
むしろ“適切な治療”で脳が守られることもある
不眠が慢性的に続くと、脳の神経活動のバランスが崩れ、ストレスやうつ、不安の温床になることが分かっています。
深い睡眠によってアミロイドβなどの脳の老廃物が排出されることがわかっています。
この機能がきちんと働かないと、将来的な認知症リスクが高まる可能性もあります。
つまり
- 不眠を放置することも、脳には悪影響
- 適切な薬物治療で眠ることができれば、むしろ脳を守る結果になりうる
という考え方もできるのです。
薬そのものより、「使い方」と「目的」が大切
睡眠薬が脳に影響を及ぼすかどうかは、
薬の種類・使い方・併用する治療・患者さんの年齢や体質によって大きく異なります。
薬を怖がる前に、まずは現在の睡眠の状態を客観的に把握し、専門的な判断を仰ぐことが、脳を守る第一歩なのかもしれません。
ウソ or ホント?:自然な眠りとはまったく違う?
「眠剤の眠りって“ニセモノ”なんですよね?」
「睡眠薬で眠っても、本当の睡眠とは違うんでしょう?」
「薬で無理やり寝かされてるだけなんじゃないか」
そう感じる方は少なくありません。
確かに、「自然な眠り」と「薬で得た眠り」は同じなのか?という問いは、直感的にも気になる点です。
ホント:薬によって“脳波”に違いがでる
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬(例:ハルシオン、レンドルミンなど)を長期投与した場合、ノンレム睡眠中に服用者特有の波長の睡眠が多く出現することが知られています(薬剤性spindle)。
その結果として「徐波睡眠(深睡眠)」が抑制される傾向があり、脳波上の睡眠構築が自然なものとやや異なることが知られていました。
現在は“自然に近い眠り”を目指した薬が主流に
しかし、近年登場した新しいタイプの睡眠薬では状況が変わっています。
自然に近い睡眠を促す新しい薬の例
| 薬のタイプ | 代表薬 | 特徴 |
| メラトニン受容体作動薬 | ラメルテオン(ロゼレム) | 生理的な眠気を促進(催眠ではなく“体内時間の調整”を行う) |
| オレキシン受容体拮抗薬 | スボレキサント(ベルソムラ)、レンボレキサント(デエビゴ) | “覚醒をオフにする”自然な睡眠リズムに沿った作用 |
これらの薬は、「強制的に眠らせる」のではなく、体のホルモン分泌リズムは通常時とほとんど変わりありません。
脳波や睡眠ステージを比較しても、自然な睡眠への影響が小さいお薬です。
大切なのは、「眠りの質を取り戻すこと」
確かに、薬によって得られる眠りが、完全に自然と同一かといえば多少の違いはあります。
しかし、それはあくまで“手段”の問題であり、“目的”は変わりません。
薬の力を借りてでも、この“目的を果たせる眠り”を得られるのであれば、
十分に意味のある睡眠であり、健康的なアプローチだといえるでしょう。
ウソ or ホント?:市販薬で代用できる?
「病院に行くのは気が重いから…」
「まずはドラッグストアで買えるもので様子を見てみよう」
「病院に行くほどじゃないし、とりあえず市販の睡眠改善薬でいっか」
そうした理由から、市販薬を使って睡眠をなんとかしようとする方も少なくありません。
テレビCMなどで「よく眠れる」とうたっている商品も多く、一見手軽で安心感があるように思えます。
でも、本当にそれだけで解決できるものでしょうか?
結論から言うとホント。
つまり、代用がうまくいくこともあります。
ただし漫然と長期間使用することはお勧めしません。
ホント:抗ヒスタミン薬でも眠りにつくことは可能
現在、日本で「睡眠改善薬」として市販されている製品は、
多くの場合、第一世代の抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミンなど)を主成分としています。
もともとはアレルギーや鼻炎の治療に使われていた薬で、
副作用として「眠気」が出やすいため、それを利用しています。
市販の睡眠改善薬の特徴
| 特徴 | 内容 |
| 主成分 | 抗ヒスタミン薬(眠気を起こす) |
| 副次的な効果 | 一時的な入眠促進(短期的) |
| 対象 | 一過性の不眠(旅行前・ストレス時など) |
| 眠気以外の副作用 | だるさ、口の渇き、翌日の眠気、注意力低下など |
禁忌疾患に注意
ジフェンヒドラミンは「抗コリン作用」という作用の影響から、閉塞隅角緑内障と前立腺肥大症の方への投与は禁忌とされています。診断を受けている患者さんは多くの場合、睡眠薬や風邪薬への注意を受けていることが多いですが、ご自身の疾患で注意を要するものがあるかどうかはかかりつけの医師へ確認しておく方がよいでしょう。
ひとむかし前は…
新規の睡眠薬(メラトニン受容体刺激薬やオレキシン受容体拮抗薬)がなかったころは、ご高齢の方への眠剤処方の代用としてジフェンヒドラミンが使われることはあったかもしれません。
しかし、抗ヒスタミン薬についても高齢者では認知機能低下のリスクが指摘されており、
「手軽さ」がかえってリスクになってしまうかもしれません。
そのため、現在では新規の睡眠薬を処方することが一般的です。
それでも一過性の不眠症状や、出先でなかなかかかりつけ医へ相談できない状況ではジフェンヒドラミンをはじめとする市販薬を使用することも選択肢の一つになるかもしれません。
原因を無視したままでは、根本解決にはならない
そうはいっても、「不眠=市販薬でOK」と安易に考えることには反対です。
不眠には、さまざまな背景があります
- ストレス・不安など心理的な要因
- 生活リズムの乱れやカフェインなど刺激物の過剰摂取
- うつ病や不安障害など、隠れた病気の一症状
- 身体の疾患や痛み
- 睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害
これらの原因を市販薬で覆い隠してしまうと、
本来の必要な治療の機会を逃す危険性があります。
一時しのぎにはなっても、“治療”にはならない
市販薬は、「どうしても今夜だけ眠りたい」といった一時的な用途には使えることもあります。
しかし、それを繰り返して使うのは、かえって問題を長引かせてしまう可能性があります。
本当に眠れない日が続いているのであれば、
自己判断ではなく、専門医に相談することが最善の近道です。
“睡眠の悩み”を放置することこそが、
心と体の健康に対して、最も大きなリスクになりかねません。
ウソ or ホント?:薬をやめるのがとても大変?
「一度飲んだら、ずっとやめられないのでは…?」
「睡眠薬って、依存性があるんですよね?」
「飲み続けていたら、二度とやめられないって聞きました」
こうしたイメージをお持ちの方も多く、睡眠薬の使用をためらう原因のひとつになっています。
確かに、「薬をやめたいのにやめられない」という状況は誰にとっても不安です。
では、それは本当に“ウソ”ではないのでしょうか?
ウソ:かつては「やめづらい薬」が多かった
こちらの答えも、今は”ウソ”です。昔はホントだったともいえるかもしれません。
以前よく使われていたベンゾジアゼピン系睡眠薬(例:レンドルミン、ハルシオンなど)には、
精神依存(薬がしばらく体に入ってこないと不安・焦りを感じる)や離脱症状のリスクがあることが知られています。
ベンゾジアゼピン系の休薬による要注意ポイント
- やめた直後に強い不眠が戻る(リバウンド不眠)
- 頭痛や不安感、焦燥、動悸
- 時には軽いけいれんのような症状
特に長期間・高用量を続けていた場合は、徐々に減薬しないと辛さを感じることもあります。
また、「やめようとすると眠れなくなる」という恐怖心が依存につながるケースも見られます。
こういった症例も、徐々に薬量を減らし、終盤には数日に1回ずつの服用にしていく「漸減療法」によって休薬することが可能ですが、代替薬のない環境で薬をやめることは本当に骨の折れる作業でした。
近年の新しい薬は「やめやすさ」も改善されている
近年は、依存性の少ないタイプの睡眠薬も登場しています。
| 薬の種類 | 例 | 離脱症状のリスク |
| メラトニン受容体作動薬 | ラメルテオン(ロゼレム) | 極めて低い(自然睡眠に近い) |
| オレキシン受容体拮抗薬 | スボレキサント(ベルソムラ)、レンボレキサント(デエビゴ) | 極めて低い(自然睡眠に近い) |
| 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | ゾルピデム(マイスリー)、エスゾピクロン(ルネスタ)など | 従来型のベンゾジアゼピン系よりは少なめ |
これらの薬では、「徐々に飲まなくてもよくなっていく」ケースも多く、計画的にやめていくことが可能です。
2022年に医学誌Lancetに掲載された170件もの睡眠薬の効果と副作用を調べたメタ解析の研究では、催眠効果の高さに加え、副作用の少なさを兼ね備えた薬剤としてレンボレキサント(デエビゴ)が最も効果的であると考えられていました。次点には非ベンゾジアゼピン系のエスゾピクロン(ルネスタ)が選ばれていました。副作用を含めた評価でもオレキシン受容体拮抗薬や非ベンゾジアゼピン系の薬剤の効果の高さがうかがえる内容でした。3)
正しい使い方なら、やめられる日が来る
睡眠薬を「ずっと飲み続けなければいけない」と決めつける必要はありません。
不眠の原因が解消されたり、生活習慣の見直しや認知行動療法(CBT-I)などを並行して行えば、
自然と薬の必要性が減り、やめられる日を目指していくことも可能です。
自己判断で急に中断するのではなく、医師と相談しながら減薬を進めていくことで、
安全に薬から卒業することを目指すことも可能です。
必要以上に睡眠薬を怖がらずに、うまく睡眠薬と付き合っていきましょう。
ウソ or ホント?:一度でも飲んだら負け?
薬に頼ったら、もう終わり?
「睡眠薬を飲んだら負けだと思っていた」
「なんだか、精神的に弱い人が飲むものというイメージがある」
「自然に眠れない自分が情けない…」
こういったイメージを持っていたと、外来でお悩みを相談した後に打ち明けてくださる方もいます。
特に几帳面で責任感の強い方ほど、薬を使うことに強い抵抗を感じやすいようです。
でも、この質問も”ウソ”。 睡眠薬=敗北ではありません。
ウソ:薬は「依存の象徴」ではなく、「快眠へのカギ」
睡眠薬は、あくまで一時的に“眠れる状態”を整えるためのツールです。
それによって、以下のような好循環が生まれます。
- 睡眠がとれることで、心の余裕が回復する
- 夜の不安が軽減し、日中の集中力や気力が戻ってくる
- 睡眠が安定すると、不眠への恐怖が弱まっていく
これは、薬による“依存”ではなく、快眠への第一歩とも言えます。
たとえば、風邪のときに解熱剤を使ったからといって「負け」だとは思いませんよね。
それと同じで、睡眠薬も「症状を和らげる手段」として位置づけるべきものです。
「薬を使うこと」より、「使わず我慢すること」の方がリスクになることも
不眠が長引くと、以下のような状態に陥ることがあります:
- 眠れない夜が続く → 焦りと不安が強まる
- 昼間にぼーっとしてミスが増える → 自信を失う
- また眠れないかもと心配になる → 緊張してさらに眠れない
このような悪循環が続くと、うつ病や不安障害の発症リスクも高まってしまいます。
「自然に眠れるようになるまで我慢する」という選択が、
かえって心身に大きなダメージを与えてしまうケースもあるのです。
「薬を使った自分」を責めないで
睡眠薬を使うことは、「弱さ」でも「敗北」でもありません。
あなたが、自分自身の健康を守るために選んだ方法です。
必要なときにサポートを受けて、少しずつ立て直していく——
それは、むしろとても勇気ある選択です。
眠れない夜にひとりで苦しむのではなく、
薬も含めた選択肢をうまく使って、自分らしい毎日を取り戻すこと。
それこそが、睡眠医療の本質だと私たちは考えています。
おわりに:使い方によって毒にも薬にもなる
睡眠は私たちの心と体を整える基本です。しかし、不眠に悩む多くの方は、「薬を使うこと」への抵抗や不安を抱えています。この記事が、そうした不安を少しでも和らげ、正しい理解につながることを願っています。
今回の説明の中で、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬に関して心配をする方が出てしまうかもしれませんが、我々は皆さんを心配にさせたいわけではありません。
ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、睡眠薬の中でも特に、不安を取り除く効果が強く、一過性の強いストレスや緊張状態への対処に適している場合があります。そのため、状況や症状によっては非常に重宝します。だからこそ、睡眠薬は自己判断で使うのではなく、医師との十分な対話をもとに処方されるのが望ましいのです。
睡眠薬は使い方によって毒にも薬なります。
睡眠薬を飲んでいる方も、そうでない方も、睡眠に関する不安や疑問を感じたら、遠慮なく専門医に相談してください。
あなたの状況や希望に合わせて最適なアドバイスや治療法を提案してくれるはずです。
一人で悩まず、適切なサポートを受けながら、質の良い睡眠と明るい毎日を取り戻していきましょう。
参考文献
- Citrome L, Juday T, Frech F, Atkins N Jr. Lemborexant for the Treatment of Insomnia: Direct and Indirect Comparisons With Other Hypnotics Using Number Needed to Treat, Number Needed to Harm, and Likelihood to Be Helped or Harmed. J Clin Psychiatry. 2021 Jun 1;82:20
- Arnold V, Ancoli-Israel S, Moline M,et al. Efficacy of Lemborexant in Adults ≥ 65 Years of Age with Insomnia Disorder. Neurol Ther. 2024 :1081-1098.
- De Crescenzo F, D’Alò GL,Cipriani A,et al. Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2022 :170-184.