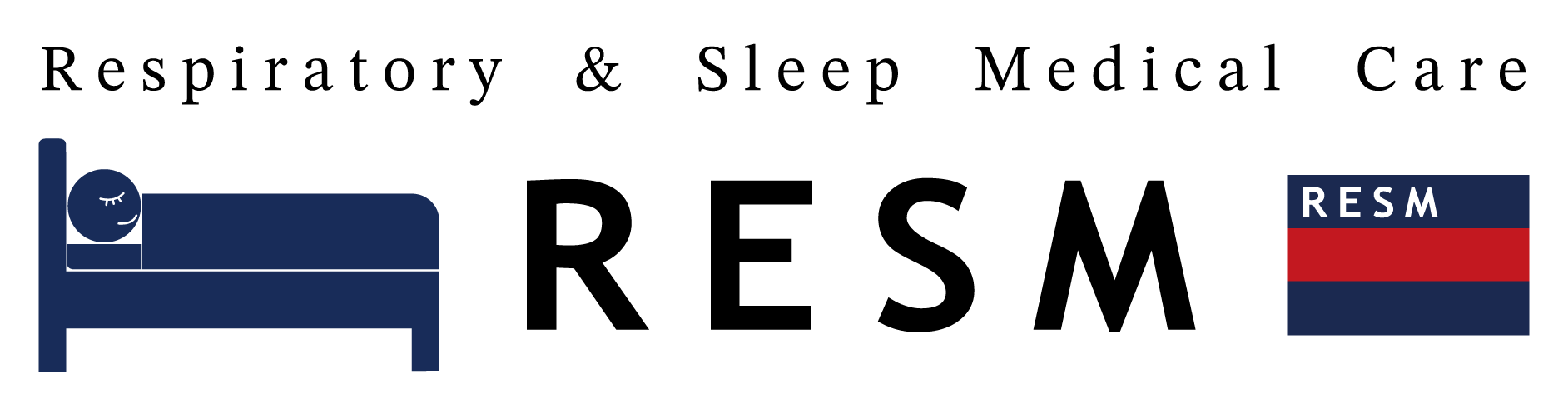【第3回】なぜ眠れない? 不眠の原因とCBT-Iでの対処法を専門医が解説
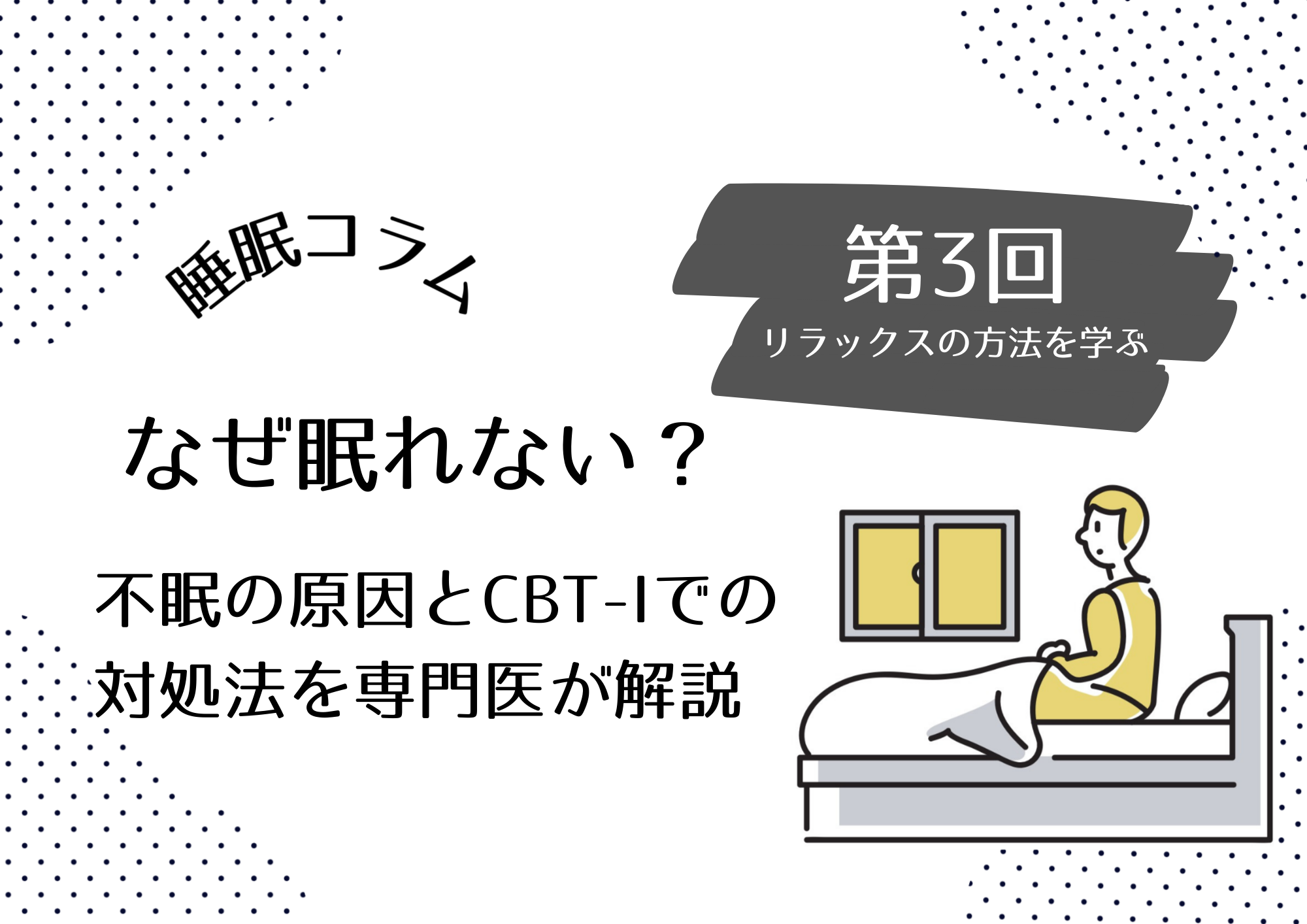
第3回:リラックスの方法を学ぶ
――筋弛緩法と自律訓練法の導入
0.マインドワンダリングとマインドフルネスについて
当院では、“マインドワンダリング”について強く懸念を抱い大きな社会問題ととらえており、
その解決策として「マインドフルネス」の取り組みを推進しています。
脳科学(神経科学)的には「心ここにあらずの状態」を「マインドワンダリング」と表現します。
心(マインド)がさまよっている(ワンダリング)というわけです。では、どうしたらそのマインドワンダリングから抜け出せるのでしょう?その解決策の1つが、瞑想であり、マインドフルネスです。
歩けば、調う 人生を豊かにする「脳と身体の休め方」 川野泰周より
スマートフォンからはたくさんの情報が受け取れます。
いい睡眠をとろうと調べればいくらでも情報を見れるいい時代だと思う反面、情報を調べないといけない時代にもなりました。
睡眠にお悩みの方の多くは、「自分はこの疾患ではないか?」と調べてから来院してくれることが多くなりました。ご自身の思った通りに診断に行き着く方もいれば、睡眠薬に関する誤った情報を手に入れて怖くなり、拒薬の結果、もっと眠れなくなる方もいます。
限られた時間でたくさんの情報を取捨選択しないといけなくなったいまだからこそ、意識的に休みを取りに行くようにすることが必要です。本日は、認知行動療法のなかから、筋弛緩法と自律訓練法についてお話していきます。
実践方法は文字だけで行うのは困難だと思われるので、RESM新横浜医院の副院長である川野泰周のマインドフルネスの実践に関する動画を下記に掲示いたします。ぜひ、文章を読み終えた後に実践してみてください。
※動画は「マインドフルネス」の実施内容です。今回お話しする内容と近い内容と考え転記しておりますが、完全な”認知行動療法”というわけではありませんのでご了承ください。
1. はじめに:「眠れない」と「リラックスできない」は同じ問題かもしれない
「目はつぶっているのに、体がずっとこわばっている気がする」
「眠らなきゃと思うほど、頭が冴えてきてしまう」
こうした訴えは、不眠の方によく見られるものです。
実は、不眠症においては「眠ることができない」以前に、“リラックスできない”という状態が背景にあることが少なくありません。
CBT-I(認知行動療法)では、睡眠に関する思い込みの修正や、生活リズムの調整に加えて、
リラクゼーション(緊張緩和)の技法を導入することがあります。
特に「神経が高ぶって眠れない」「布団に入ると緊張する」といった傾向が強い方にとって、
このパートは治療の大きな助けになります。
2. 「緊張」と「眠り」は反対のプロセス
人間の自律神経には、活動時に働く「交感神経」と、休息時に働く「副交感神経」があります。
眠りに入るには、交感神経の興奮が鎮まり、副交感神経が優位になる必要があります。
しかし、不眠に悩む方の多くは、
- 寝る前に「また眠れなかったらどうしよう」と不安になる
- 寝つけないことでさらに緊張し、焦る
- 体のこわばりや浅い呼吸が続き、リラックスできない
といった悪循環に陥りがちです。
そのため、CBT-Iでは「考え方」や「行動」のアプローチに加えて、
身体レベルでの“緩み”を作る技法として、筋弛緩法や自律訓練法を用いることがあります。
3. 筋弛緩法(PMR:Progressive Muscle Relaxation)
基本的な考え方
筋弛緩法は「力を入れる→抜く」を繰り返すことで、
筋肉の緊張と弛緩の感覚を意識的に体験し、脱力状態を引き出す方法です。
一時的に筋肉を緊張させることで、かえって深くリラックスできるようになります。
実施のステップ
- 静かな場所で、楽な姿勢を取ります(椅子に座るか、仰向け)
- 手のひらを握りしめ、5秒キープ → 力を抜いて10秒脱力(腕全体の重さを感じる)
- 顔、肩、腹部、太もも、ふくらはぎなど、身体の各部位を順に緊張→脱力
- 呼吸をゆっくり、自然に保ちつつ、全身の緩みを感じる
ワンポイント
無理に“力を抜こう”とする必要はありません。
「抜けている感じがするなあ」と思える程度で十分です。
注意点と適応
- 痛みや違和感がある部位には無理な力を入れないこと
- 初回ではリラックスを実感しにくいこともありますが、継続するほど自動的に“脱力スイッチ”が入りやすくなります
- 数日試しただけではしっくりこないかもしれませんが、毎日行っていくことで徐々にリラックスが効いてきます
4. 自律訓練法(AT:Autogenic Training)
技法の原理
自律訓練法は、1930年代にドイツの精神科医シュルツが開発した技法で、
「自己暗示」によって心身を深くリラックスさせる方法です。
身体の各部に「重い」「温かい」といった感覚を意識的に誘導し、
副交感神経を優位に導くことで、自律神経の安定を目指します。
6つの公式と進行
- 安静練習:「私は静かに落ち着いている」
- 重感:「両腕が重たい」「両脚が重たい」
- 温感:「両腕が温かい」「両脚が温かい」
- 心臓調整:「心臓が静かに打っている」
- 呼吸調整:「呼吸が楽になっている」
- 腹部調整:「お腹が心地よく温かい」
実践のコツ
声に出す必要はありません。
心の中で、ゆっくり、繰り返し唱えるように意識します。
習得のポイント
- 最初は「重さ」「温かさ」を感じにくくてもOK
- 感じようとするよりも、「そう唱えるだけでいい」と考えるほうが効果的です
- 習得にはある程度の練習期間(数週間以上)が必要です
過ごしていくうちに、別の考え事が思い浮かぶことがあると思います。
そんな時は思い浮かんだ内容を消そうとしないで、
“ああ、〇〇のことを思い出しているんだな” と思い浮かんだことを受け止めて、唱える作業を繰り返していきます。
※”なにも考えないぞ!!”とこわばるとうまくいきません
こうして、”過去”のいやなこと、”これから”の不眠に対する不安などから意識的な距離を作って、「今」という時間、体の感覚に集中していくことがコツだと考えます。
この考え方は冒頭でご説明したマインドフルネスにも共通の考え方です。
過度に昔や将来のことに不安になりすぎないように意識を今に向けていきましょう。
※筋弛緩法と同様に継続するほど自動的に“スイッチ”が入りやすくなります。毎日行っていくことで徐々に唱えている内容以外のことが頭に浮かびづらくなり、寝つきやすい状態に近づきます。
5. CBT-Iにおけるリラクゼーション技法の役割
CBT-Iでは、リラクゼーション技法は「治療の中心」ではありませんが、
「眠れない夜を過ごす自分」とどう向き合うかの補助線として非常に有効です。
特に、「頭が冴えて止まらない」「布団に入ると緊張してしまう」という方にとっては、
“考えを変える”よりも“身体から緩める”方が、即効性を感じやすいこともあります。
また、筋弛緩法や自律訓練法は、
- 寝る前のルーティンとして
- 日中の不安感の緩和として
- 寝つけない夜の“切り替え手段”として
など、睡眠時間だけでなく、日常生活の中で活用できる手段となります。
6. おわりに:リラックスとは“頑張らない”スキル
「リラックスしよう」と頑張ってしまうと、かえって緊張が増します。
このジレンマを超えるために必要なのは、“力を抜く”練習を少しずつ、毎日行うことです。
筋弛緩法や自律訓練法は、「今は眠れなくてもいい」と自分に許すための、
“ゆとり”の時間でもあります。
眠りは、コントロールしようとするほど逃げていきます。
だからこそ、「眠ろうとしない練習」こそが、良い睡眠への第一歩になるのです。