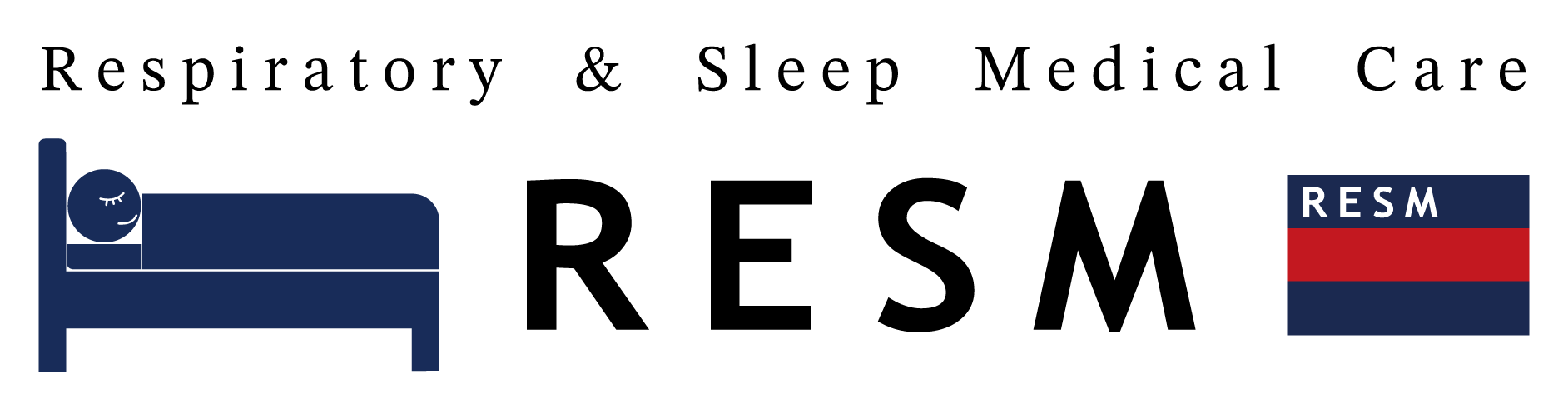【第5回:最終回】なぜ眠れない? 不眠の原因とCBT-Iでの対処法を専門医が解説
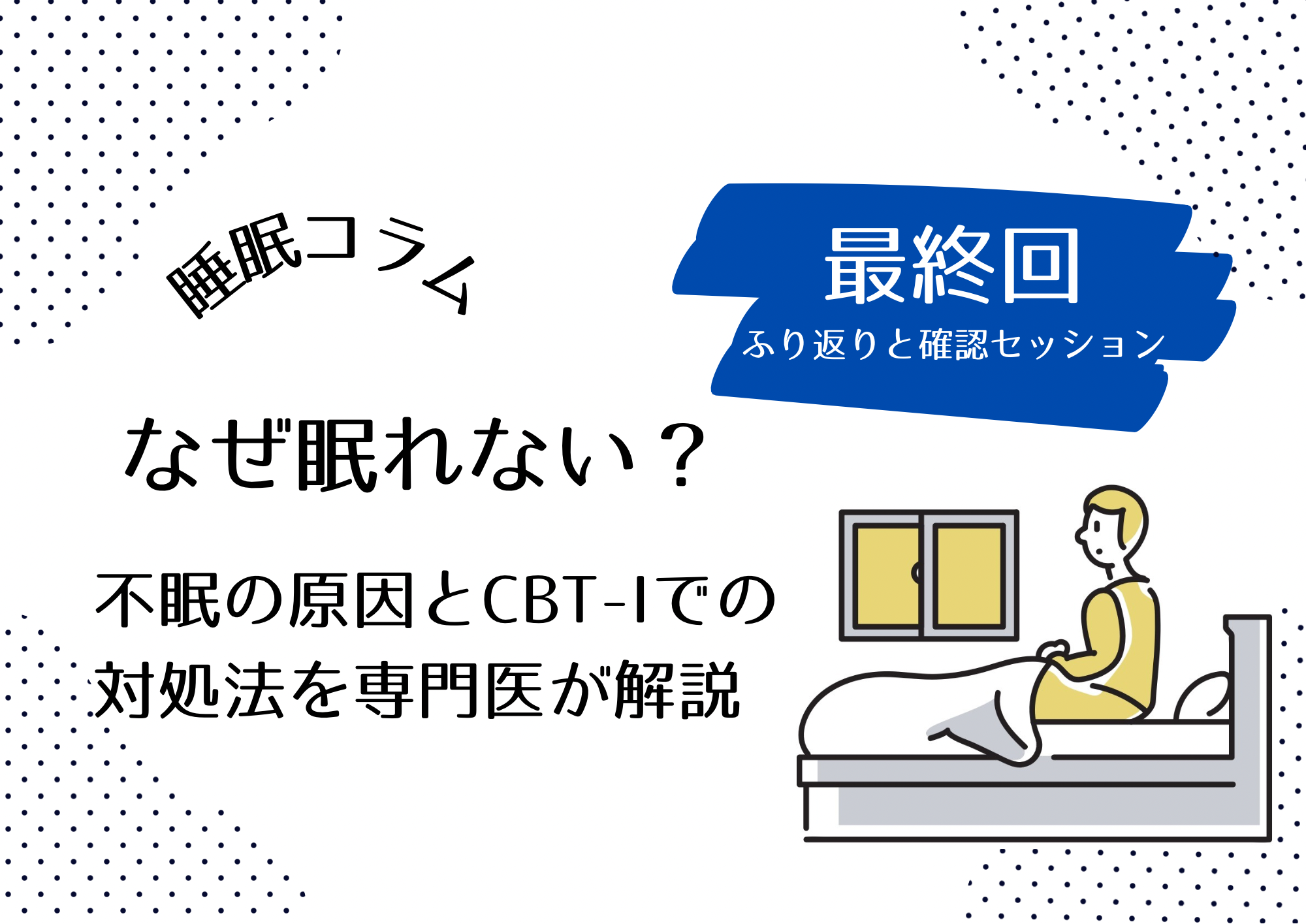
5回:ふり返りと確認セッション
1. はじめに:5回のセッションを終えるにあたって
CBT-I(不眠に対する認知行動療法)は、通常5-6回の短期プログラムです。
けれども、私たちの「眠りとの関係」は、それだけで終わるものではありません。
むしろ、これまで学んだことをどう日常に根づかせていくか――
ここからが「ほんとうの変化」のスタート地点です。
この最終回では、これまでの取り組みを一緒にふり返りながら、
これからも続く“眠りとのつきあい”をサポートする準備を整えていきます。
2. 自分の変化に目を向ける
行動の変化
最初の頃と比べて、次のような行動面に変化はあったでしょうか?
- 昼夜様々だった起床時間が、同じ時間にまとまるようになった
- 就寝前のルーティンがきまり、就寝前に感じていた緊張感が和らいでいる
- 寝床での「目覚めている時間」が減ってきた
睡眠日誌を見返すことで、数字の上でも進歩が見えるかもしれません。
小さな変化でも、それが継続できていれば立派な成果です。
思考の変化
「眠れなかった=もうダメだ」という極端な考え方が、
「眠れない日もあるけど、うまく対処できる」と柔らかくなっていたら、
それは認知の再構成が根づいてきた証拠です。
第3回のセッションでもお話ししましたが、うまく眠れないときも深く落ち込まずに、
その時の感情を”受け止めること”が大切です。
数日ではなく、数か月もの間自分自身の眠りについて目をむてきたことで、
きっと睡眠について前向きにとらえなおすことができるようなっているはずです。
不眠そのものではなく、「不眠への反応」が変わったかどうか、
そこに注目してみてください。
3. 継続のコツと落とし穴
CBT-Iは一度で完結する“特効薬”ではなく、
セルフマネジメントの技術を身につけるためのプログラムです。
ここでは、今後も続けていくうえでの「コツ」と「注意点」を整理します。
続けてほしいこと
- 起床時間を一定に保つ
- 寝る前のスクリーン時間を控える
- 「眠くなってから布団へ」など刺激制御法を意識する
- 不安な思考が出たら、自律訓練法などでも対処する
CBT-Iで得た習慣や視点のうち、「これは効いた」と思えるものは、
日々の生活に無理のない範囲で取り入れ続けましょう。
対処の方法は一つではありません。
今まで記載したものだけでなく、睡眠について向き合ったあなただけの対処策もあるかもしれません。
有効だった方法はぜひ取り組み続けていきましょう。
陥りやすい注意点
- 睡眠時間や入眠までの時間への”過剰な”こだわりが戻る
- 「また眠れないかもしれない」と不安が強まる
- 日中の活動量が落ち、疲れを感じにくくなってくる
そうした変化に気づいたら、「また最初のステップに戻ってよい」と自分に許可を出してください。
ふり出しに戻るのではなく、「学んだ上で立ち戻る」ことができるのがCBT-Iの強みです。
4. 自分なりの再発予防プランをつくる
不眠には「再燃(ぶり返し)」がつきものです。
それは失敗ではなく、ごく自然なことです。
再発しやすいタイミングを予測する
- 大きな環境の変化(転職、引っ越し、人間関係)
- 体調不良や生活リズムの乱れ
- 睡眠への“意識過剰”が戻ってきたとき
こうしたタイミングに備えて、
「こんな時はこう対処する」とあらかじめ考えておくと安心です。
数年たって再び不眠に悩んだ時、
「また相談してもいいんだ」と思えることも、予防策の一つです。
変化を持続させるために、“ひとりで抱えすぎない”工夫も大切にしてください。
5. おわりに:終わりは、新しい関係のはじまり
CBT-Iのゴールは、「不眠を完全になくすこと」ではありません。
そうではなく、“眠れない夜があっても自分で対応できる力”を育てること。
この5回で得た知識や習慣、視点は、
きっとこれからのあなたを支える“道具”となるはずです。
完璧な眠りではなく、
「眠りとうまくつきあっていける自分」を目指して、
どうかこれからも、少しずつ進んでいきましょう。